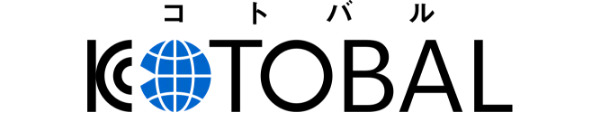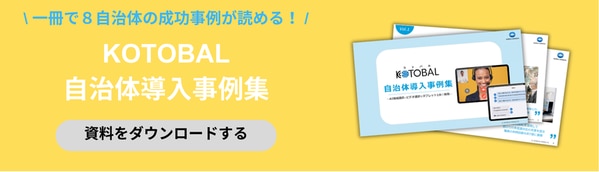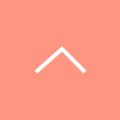多文化共生の課題とは。多様性を受け入れる地域社会を実現するには

近年、少子高齢化に起因する人手不足やグローバル化の進展のなかで、多文化共生が重要となっています。多文化共生とは、国籍や民族などが異なる人々が、文化的な違いを認め合ったうえで対等な関係性の構築を図りながら、ともに生きていくことです。
自治体においては、多文化共生を可能とする地域社会の実現が求められます。しかし、多文化共生に向けては、さまざまな課題もあります。
この記事では、地域における多文化共生について、求められる理由や課題、課題解決のポイントを解説します。
多文化共生が求められる理由
多文化共生が求められる理由としては、以下が挙げられます。
▼多文化共生が求められる理由
● 人手不足を補うために外国人労働者の受け入れが進んでいる
● グローバル化のなかでダイバーシティの推進が求められている
● SDGs(※)に多文化共生と関連する項目がある など
人手不足を補うために外国人労働者の受け入れを推進する制度の整備が進んでおり、2023年の10月時点で2,048,675人もの外国人労働者が日本に在住しています。
また、多様性を重視するダイバーシティの推進が世界的に求められるなか、SDGs(※)においても多文化共生に関連する目標が設けられています。
▼多文化共生に関連するSDGsの目標
● すべての人に健康と福祉を
● 質の高い教育をみんなに
● 働きがいも経済成長も
● 人や国の不平等をなくそう
● 住み続けられるまちづくりを
● 平和と公正をすべての人に
※SDGsは、Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された国際的な開発目標です。
出典:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)』/法務省『意見書~共生社会の在り方及び中長期的な課題について~』
多文化共生の実現を目指すうえでの課題
地域において多文化共生の実現を目指すうえでの課題として、情報の入手がスムーズに行えないことや、文化・宗教の違い、雇用・教育制度の不足などが挙げられます。
また、言語の壁によって悩みごとに関する相談そのものが難しくなっていることも課題といえます。
外国人向けの情報がうまく伝わっていない
国や自治体で在住外国人向けに発信している情報について、内容や発信媒体が原因でうまく伝わっていないケースが見られます。
▼国・自治体による情報発信に関する課題
● 法律用語が多用されていて理解が難しい
● 窓口やWebサイトが細分化されていて情報がまとまっていない など
国・自治体が外国人向けに発信する情報には医療や法律などに関する情報も含まれていることから、円滑な情報伝達を行える体制の構築が求められます。
文化や宗教の違いによるトラブル
文化や宗教の違いから、互いのことが理解できずにトラブルにつながるケースが見られます。
▼文化や宗教の違いによるトラブルの例
● 外国人に疎外感を与える発言を日本人が無意識にしてしまう
● 日本人にとって暗黙のルールを外国人が破ってしまい、疎外される など
互いの文化・宗教への理解不足から誤解につながり、最終的には対立に発展してしまう可能性もあります。
雇用や教育に関する制度の不足
在住外国人に対する雇用や教育のサポートが十分でないことで、就職が困難になったり、学習にハンデを背負ったりする場合があります。
▼雇用・教育に関する課題の例
● スキルに応じた仕事の情報を得ることが難しい
● 両親の母国語が日本語でないことで、国語の成績に影響が生じる など
言語の壁によるコミュニケーションの問題
言語の壁によってコミュニケーションが円滑に行えないことで、悩みやトラブルがあったとしてもうまく相談を行えないケースが見られます。
法務省が行った2023年度の『在留外国人に対する基礎調査』によると、家族・友人あるいは所属する企業・機関に相談を行う際に「言語の問題で正確な意思疎通が難しい」と感じた率はそれぞれ23.7%、36.1%と高い水準になっています。
出典:法務省『令和5年度 在留外国人に対する基礎調査』
多文化共生の課題解決を図るポイント
多文化共生の課題解決を図るには、情報発信や支援の体制づくりや外国人への理解促進の施策を行うことが重要です。また、行政窓口の多言語対応も欠かせません。
①外国人目線での情報発信
国・自治体から発信する情報を在住外国人に確実に受け取ってもらうためには、情報の内容や伝え方、発信媒体などを工夫する必要があります。
▼外国人目線での情報発信の例
● 発信する情報の基準をガイドラインで明確にする
● 文字情報だけでなく図やイラストによる視覚情報も活用する
● マイナポータルを利用して情報を発信する など
②多文化に対する理解の促進
ほかの文化・宗教への理解を促進する施策を実施すると、無理解による差別や偏見が生じることを防ぎやすくなると期待できます。
▼多文化に対する理解促進の施策例
● 在住外国人と日本人住民が互いの文化を学べるイベントを実施する
● 外国人とのコミュニケーションツールとして、やさしい日本語の導入を推進する
● 学校教育において多文化共生の啓発を行う など
③ライフステージの移り変わりに応じた支援
多文化共生を実現するには、在住外国人の加齢に伴うライフステージの移り変わりに合わせて、教育や就労に関する支援を行っていくことが重要です。
▼ライフステージの移り変わりに応じた支援の例
段階 |
支援内容 |
乳幼児期 |
外国人の親子が地域社会で孤立しないための実態調査・環境整備 |
学齢期 |
外国人家庭の子どもを対象とした日本語学習の支援 |
青壮年期 |
就労の安定やキャリアアップを支援する研修や職業訓練制度の提供 |
④行政窓口の多言語対応
自治体においては多言語対応の相談窓口を設けることで、在住外国人がかかえる悩みやトラブルを把握して対応できるようになります。
ただし、外国人の増加や国籍の多様化によって多言語に対応するための通訳を確保することが困難なケースも考えられます。
多言語通訳サービスを自治体に導入すると、自治体の職員が積極的に在住外国人とコミュニケーションを取れるようになります。また、通訳の数が足りない言語への対応も可能です。
コニカミノルタが提供する『KOTOBAL(コトバル)』は、AIによる機械通訳とオペレーターによるビデオ通訳の機能が備わったハイブリッド通訳サービスです。タブレットやスマートフォンで入力した音声・テキストについて、自動で通訳を行えます。
地方自治体向けの翻訳・通訳サービスについてはこちらの資料をご確認ください。
まとめ
この記事では、地域における多文化共生について以下の内容を解説しました。
● 多文化共生が求められる理由
● 多文化共生の実現を目指すうえでの課題
● 多文化共生の課題解決を図るためのポイント
少子高齢化による人手不足やグローバル化の流れのなかで日本における外国人労働者の数は増加傾向にあり、自治体においては外国人との多文化共生を実現するための対策が求められます。
多文化共生を実現するには、生活に必要な情報提供や多文化に対する理解の促進、ライフステージに応じた支援などが欠かせません。
また、行政窓口を多言語対応すると、在住外国人の課題を自治体で把握して対応しやすくなります。
『KOTOBAL(コトバル)』は、タブレット1台で最大32カ国の外国語をリアルタイムで通訳・翻訳できるサービスです。話し手が変わるたびにボタンの操作やマイクの切り替えをすることなく、透明ディスプレイを介してハンズフリーでのリアルタイムな通訳・翻訳を行えるため、スムーズなコミュニケーションを実現できます。
また、KOTOBALの『やさしい日本語AI音声翻訳サービス』では、日本語がネイティブではない方でも分かりやすい、簡単な日本語を使った文章に翻訳することが可能です。自治体の窓口において外国人への対応を行う際にもご活用いただけます。
KOTOBALの自治体導入事例については、以下の資料をご確認ください。
ハイブリッド多言語通訳サービス『KOTOBAL』

KOTOBAL(コトバル)は、コニカミノルタが開発した通訳サービスです。
AI機械翻訳とオペレーターによるハイブリッド通訳で、最大32カ国の外国語対応と音声筆談・手話通訳を、タブレット1台で導入可能。
外国人だけでなく、高齢者・障がい者まで、自治体・ホテル・金融機関の窓口業務において、誰ひとり取り残さないコミュニケーションの実現をサポートします。