障がい者人口の増加と法制度の変化をきっかけに、窓口対応の見直しを検討
障がい者数の増加に加え、「障害者差別解消法」の改正や「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行といった法制度の変化を受け、自治体としても“合理的配慮”や“情報保障”の強化が求められる時代に。誰にでも“伝わる”窓口対応の実現を目指し、KOTOBAL導入の検討が進みました。

 東京都 板橋区役所 福祉部 障がい政策課様
満足度90%超、他部署でも活躍。
東京都 板橋区役所 福祉部 障がい政策課様
満足度90%超、他部署でも活躍。人口約58万人の大都市・板橋区では、障がい者支援や外国人住民への対応力強化を目的に、窓口対応の見直しを進行。その中核として、遠隔手話・AI翻訳・音声筆談が一体化した通訳サービス「KOTOBAL」を導入。
現在では区内複数部署で運用され、住民・職員ともに90%を超える高い満足度を獲得しています。今回は、障がい政策課の柴﨑様・三波様・志垣様にお話を伺いました。
※取材:2025年1月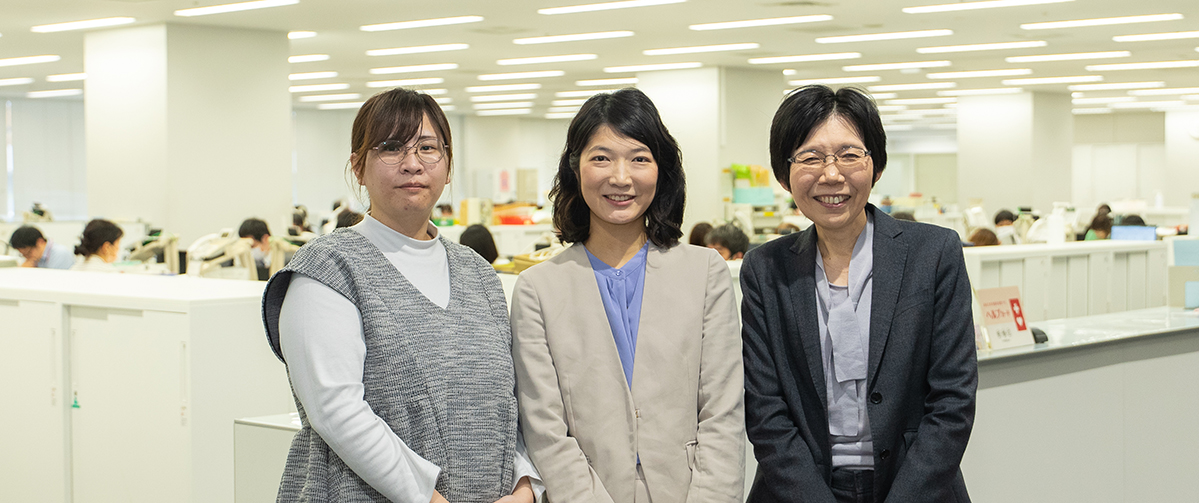

障がい者数の増加に加え、「障害者差別解消法」の改正や「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行といった法制度の変化を受け、自治体としても“合理的配慮”や“情報保障”の強化が求められる時代に。誰にでも“伝わる”窓口対応の実現を目指し、KOTOBAL導入の検討が進みました。
手話人材の確保が困難な中、時代に即したICTソリューションとしてKOTOBALが候補に。
三波様:人材不足の中で手話相談員を増やすのは現実的に難しく、当初は職員が作る指差しボードで対応する案も出ました。
ですが、「今の時代に合った方法を使うべきでは」と協議していたタイミングで、コニカミノルタの担当の方と出会い、KOTOBALを知りました。
他社の遠隔手話や音声筆談ツールも比較しましたが、KOTOBALは遠隔手話、32言語対応のAI通訳、ビデオ通訳まで揃っており、外国人対応にも活用できる点が決め手になりました。
小さな文字や下向きの視線で伝わりづらかった従来のツールに比べ、KOTOBALは真正面での視線と読みやすさがコミュニケーションを後押し。
三波様:タブレットだと文字が小さくて見づらく、目線が下に向いてしまうためコミュニケーションが取りにくい状態でした。
しかし、KOTOBALの透明ディスプレイなら、顔を見合わせながら自然に対話ができる。窓口に置けるサイズ感も絶妙です。
障がい者支援機能の移管や来庁者数の多い部署への配置により、区内全体での運用が進行中。
三波様:組織改正で福祉事務所にいた手話相談員が他部署へ異動したため、その補完として福祉事務所にもKOTOBALを配置しました。
また、外国人の来庁が多い戸籍住民課では、多言語翻訳・ビデオ通訳が活用できると考え導入を決定。障がい政策課には、他部署用の貸し出し機も設置しています。
機能理解を促す説明会の実施により、翻訳精度の高さと逆翻訳機能への支持が広がる。
志垣様:戸籍住民課では、他社の翻訳機が先に導入されていたこともあり、最初は利用が伸びませんでした。
ですが、KOTOBALの説明会を実施したところ、「翻訳が正確」「逆翻訳で確認できるのがありがたい」と高評価をいただけました。
住民・職員向けアンケートで90%以上の満足度を獲得。コミュニケーション改善の手応えを実感。
志垣様:住民向けのアンケートでは、93%の方が「満足」と回答されました。
さらに職員向けでは、使用経験のある職員のうち97%が「導入前よりコミュニケーションが伝わりやすくなった」と答えており、非常に高い評価を得ています。
妊産婦の訪問支援や生活保護の面談支援などでは、KOTOBALのビデオ通訳機能が特に重宝されています。さらには、聴覚障がい職員の情報保障にも寄与。
志垣様:訪問時の活用も増えており、外国籍の妊産婦宅や生活保護の面談などで貸し出し依頼が多く寄せられています。
また、行政用語をKOTOBALで正確に文字起こしできるため、聴覚障がいのある職員からも「スマホアプリよりわかりやすい」と好評です。


体験会や貸出運用に加え、デジタル田園都市国家構想交付金(デジ田交付金)などの補助金も活用しながら、庁内全体へKOTOBALの導入を進める取り組みを加速。
志垣様:KOTOBALは、人手不足の課題にも対応しながら、職員と住民の両方の安心感を支えてくれる存在です。庁内体験会などを通じて利用者が増えていますので、今後も周知活動を続け、活用の輪を広げていきたいです。
柴﨑様:障がい政策課だけでなく、他の部署からも「貸してください」と言われるたびに、導入して良かったと感じます。KOTOBALが職員・住民の双方にとって“伝わる”安心を提供するインフラになってくれたらうれしいですね。
柴﨑様:板橋区は年々、障がいのある方の人口が増加しており、多くの方が区役所へ来庁されています。そうした中で、手話相談員が不在のタイミングでもスムーズに対応できる体制づくりが課題でした。
「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の影響もあり、情報保障のあり方を見直すきっかけになりました。